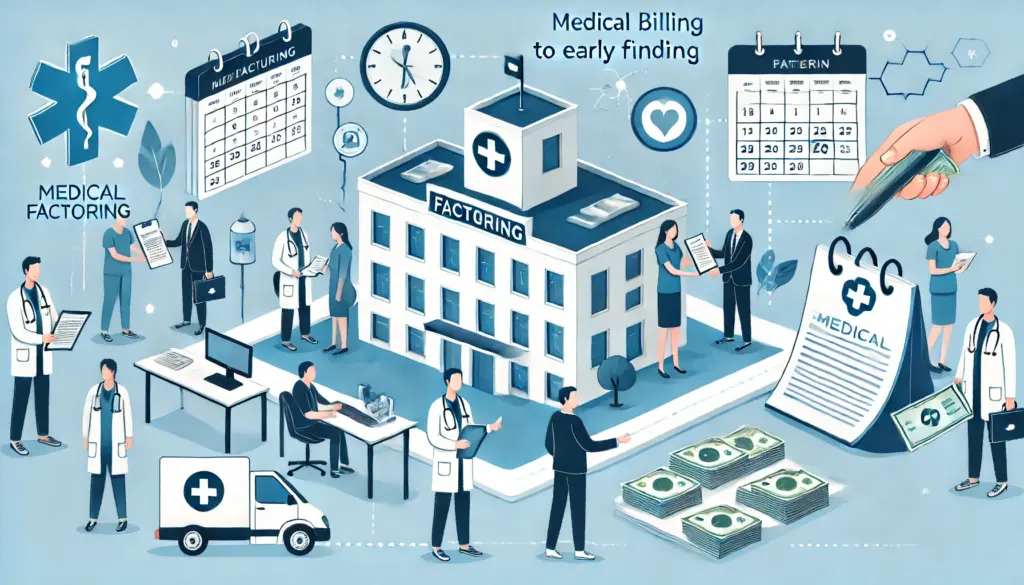
高齢化社会が進む日本において、病院・診療所・介護施設といった医療福祉機関の経営は年々複雑さを増しています。特に診療報酬の入金までにタイムラグがあることから、資金繰りの悩みは常に付きまといます。そんな中で注目されているのが「医療ファクタリング」という資金調達手法です。
この記事では、医療ファクタリングの基本から仕組み、メリット・デメリット、導入事例、注意点までをわかりやすく解説します。
医療ファクタリングとは?
医療ファクタリングとは、医療機関が国民健康保険団体連合会(国保連)や社会保険診療報酬支払基金(支払基金)に対して有する診療報酬債権をファクタリング会社に売却し、期日前に資金化する仕組みです。
医療報酬は通常、レセプト(診療報酬明細書)を提出してから入金までに1〜2ヶ月程度かかるため、その期間の資金繰りを補う手段として活用されます。
医療業界に特有の資金繰り課題
1. 入金までのタイムラグ
- 診療報酬は月末締め・翌月以降支払い
- 国保連・支払基金の処理に時間がかかる
2. 突発的な支出
- 医療機器の修繕・更新費用
- 医薬品・衛生資材の大量仕入れ
- スタッフの賞与や人件費支払い
3. 融資のハードル
- 金融機関による担保・保証人の要求
- 赤字経営や短期的な業績悪化により審査通過が難しい
こうした課題を背景に、売掛金にあたる診療報酬債権を用いて早期に資金調達できるファクタリングが注目されています。
医療ファクタリングの仕組み
基本的には、以下のような流れで進行します。
- 医療機関がレセプトをファクタリング会社に提出
- 審査のうえ、診療報酬債権を買い取る契約を締結
- 手数料を差し引いた金額が最短即日で入金
- 後日、国保連・支払基金からファクタリング会社へ本来の診療報酬が支払われる
このように、ファクタリング会社が診療報酬の入金を“肩代わり”する形になるため、医療機関側は早期の資金確保が可能になります。
医療ファクタリングの種類:2者間と3者間
| 区分 | 特徴 | 向いている施設 |
|---|---|---|
| 2者間ファクタリング | 売却先(支払基金等)に通知せず契約 | 中小規模のクリニック・急ぎの資金ニーズ |
| 3者間ファクタリング | 売却先に通知・承諾を得る形式 | 大型病院や取引信用を重視する法人 |
医療ファクタリングのメリット
- 即日資金化が可能(最短1日)
- 借入ではないため、信用情報に影響しない
- 担保・保証人不要
- 赤字経営でも利用可能
- 人件費や医薬品の仕入れなど用途自由
導入事例(例)
Aクリニック(内科)
- 月商:約600万円/運転資金確保のために月1回ファクタリングを実施
- ファクタリング手数料:2.5%/回
- 担保・保証人なし/審査書類はレセプト写しと決算書のみ
B法人(介護付き有料老人ホーム)
- 国保連請求分:約1,200万円
- 手数料は3者間ファクタリングで1.5%
- 入金サイクルが安定し、金融機関の信用評価も上昇
医療ファクタリングの注意点・デメリット
1. 手数料が発生する(相場:1〜5%)
あくまで売掛債権の買取なので、融資に比べてコストが高め。ただし迅速性と担保不要のメリットと天秤にかける必要があります。
2. 悪質業者の存在
一部では「名ばかりファクタリング」として高利貸しに近いサービスも。金融庁・中小企業庁が注意喚起を出しています。
3. 情報管理リスク
医療データ・請求情報の取り扱いには細心の注意が必要。信頼できる会社かどうかの見極めが必須です。
導入前に確認すべきチェックポイント
- ファクタリング会社の実績・医療業界対応歴
- 手数料体系(隠れコストの有無)
- 入金スピードと契約書の明確性
- 個人情報・レセプト管理体制
- 2者間/3者間の選択肢と通知義務
医療ファクタリングは、診療報酬という安定した売掛債権を活用できることから、非常に相性のよい資金調達手段です。入金までのタイムラグを解消し、キャッシュフローを安定させることで、地域医療の継続や職員の雇用維持にも寄与します。
導入にあたっては、信頼できる業者選定と正確な契約内容の把握が不可欠です。補助金や税務面の影響もふまえつつ、自院にとって最適な資金戦略を考えるうえで、医療ファクタリングは“選択肢の一つ”から“当たり前の選択肢”になりつつあります。

